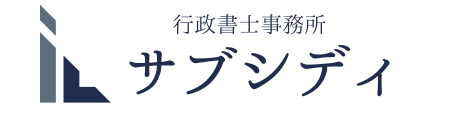近年、金融機関の融資姿勢は金利動向や経済環境の変化により大きく変わりつつあります。
当事務所でも、直近の資金調達に関するお問い合わせでは「いつもより審査が厳しい」「追加融資の見通しが立たない」といった声が増えており、多くの中小企業が同じ課題に直面している状況です。
本記事では、実際に当事務所へ寄せられる相談内容を踏まえながら、金融機関の融資姿勢がなぜ変化しているのか、その影響をどう受け止め、どのように備えるべきかを整理しています。
資金調達に不安を抱える方や、今後の融資を検討されている方に向けてまとめた内容となりますので、参考にしていただければ幸いです。
金融機関の融資姿勢はなぜ変化しているのか
近年、金融機関の融資姿勢が変化している背景には、金利上昇や物価高、人件費の増加といった外部環境の変化があります。
これにより企業の収益が不安定になり、金融機関としても従来より慎重なリスク管理が求められています。
また、一時的に緩和されていた審査基準が「平常化」したことで、以前よりも事業の安定性や返済能力を厳しく確認する場面が増えています。
業種によって業績差が大きくなっていることも影響し、金融機関は企業の将来性や資金繰りの見通しをこれまで以上に重視するようになっています。
融資姿勢の変化が中小企業に与える影響と備え方
金融機関の融資姿勢が厳しくなると、中小企業は「必要なタイミングで必要な資金が確保できない」というリスクに直面します。
とくに追加融資やつなぎ資金を必要とする場面では、審査期間が以前より長くなったり、希望額が満額融資されないなど、資金繰りに直接影響するケースが増えています。
また、決算内容が良くない企業や、売上に季節変動がある企業は、審査のハードルがさらに高くなりやすく、資金繰りのブレがそのまま信用力の低下につながりかねません。
企業側が「ギリギリになってから資金調達を検討する」ことが最も避けるべきリスクとなります。
日頃から売上の見通しや支出計画を明確にし、資金繰り表を定期的に更新することで、早期に資金ショートの兆候を把握できます。
また、決算内容や事業計画を丁寧に説明し、金融機関と継続的なコミュニケーションを取ることも大切です。
さらに、複数の資金調達手段を組み合わせておくことで、特定の金融機関に依存しない体制を作れます。前もった備えが、融資姿勢が厳しい局面でも資金繰りを安定させ、事業継続の大きな支えとなります。
専門家に伺った、金融機関の在り方と企業が知っておくべきポイント
金融機関を取り巻く環境は、社会情勢や経済状況の変化とともに大きく動いています。
こうした変化の中で、金融機関がどのような役割を果たし、どのような視点で企業や個人と向き合っているのかや今後の動向を理解することは、事業運営において欠かせません。
本章では、金融を専門とする有識者に伺いながら、金融機関の在り方と、その背景にある考え方を学んでいきましょう。

齊藤 直 教授
(フェリス女学院大学 グローバル教養学部)
金利が上がる時代に、企業が今から考えておきたいこと
「金利のある世界」というごく普通の状態を示す表現が世間で強調されている事実は、「金利のない世界」が長く続いたことを示しています。非伝統的金融政策が導入されてから4半世紀以上が経過し、異次元金融緩和が採用されてからでも干支が一周しています。
「金利のない世界」を長く過ごした企業にとって、金利の上昇に大きな負担感があることは確かでしょう。しかし、金融機関の側では、金利の上昇により、融資に対する姿勢が積極化すると見込まれます。これは企業にとって融資を受けやすい状況を意味します。すなわち、企業にとっても金利の上昇は悪いことばかりではありません。
もっとも、現在は金利の上昇が始まって間もない時期にあたります。融資を受けやすくなるのはもう少し先のことかもしれません。月並みではありますが、その時まで、上昇した金利分を吸収できるように自社の収益力を高めることが重要になるでしょう。
広がる金融機関の預金基盤強化への取組み
金融機関の預金・貸出動向をみると、長期にわたり個人年金の流入や企業預金の増加などから預金が順調な一方、貸出は先行き経済への不透明感を背景に伸び悩む構図が続き、多くの金融機関は貸出を最優先に取り組んできた。
しかし近年、人口減少を背景とした地方から都会への預金流出、ゼロゼロ融資に伴う派生預金の解消、さらには預金以外の商品への資金シフトなどから、預金の前年比は鈍化傾向をたどっており、特に信用金庫では2025年6月以降、預金の前年比がマイナスとなるなど、かつてとは様変わりの状況になっている。
一方、貸出については金利が上昇傾向にある中、堅調に推移している。こうした状況変化を背景に、預金基盤強化の取組みが一段と広がっていくこととなろう。

植林 茂 教授
(椙山女学園大学 現代マネジメント学部)

坂和 秀晃 准教授
(名古屋市立大学 経済学研究科)
金融機関の現在のあり方や経営環境の変化
金融機関の現在のあり方は、社会の「デジタル化」の進行とともに変化しています。決済・送金の現場では、キャッシュレス取引が増加しています。金融機関の融資の現場でも、従来型の過去の決算などの「財務情報」などをベースに借入の審査を行う方式から、日々の「取引情報」を基に融資の審査を行う方式(トランズアクション・レンディング)への変容が起こっています。
金融機関を巡る環境は、「デジタル化」の進展により、支店をもたないインターネット専業銀行であるイオン銀行やセブン銀行なども決済・融資業務を提供しています。
このように、金融機関が、異業種との競争を行うような経営環境の変化の中で、「どのようにデジタル化に向き合うか?」が今後の重要な経営課題になってきます。